スポンサーリンク
リレー(継電器)の構造や使い方について解説致します。
コイル側に通電される電力によってコイルを電磁石にし
磁力によって引きつけられた金属片が接点をON/OFF
させることにより、小さい電気的信号を大きな信号出力
にする電気部品です。
○接点の種類
接点には、A接点とB接点があります。
A接点はコイルに電圧が加わった時にONになる接点です。
B接点はコイルに無通電状態(常時)でONになる接点です。
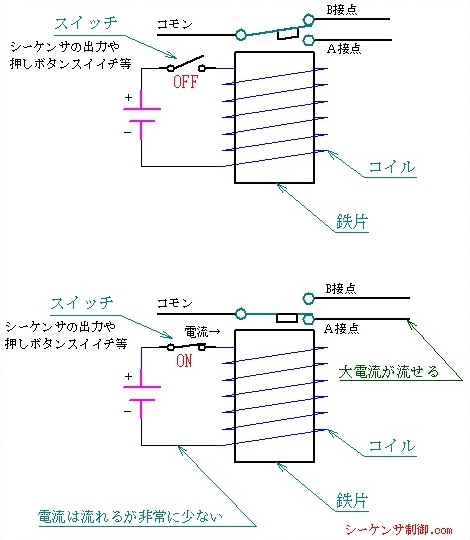
上の図で説明致します。
上側のリレーはコイル側のスイッチがOFFなので、電流が流れず
電磁石にはなっていません。接点は自分自身のバネでB接点側に接続
されています。
下側のリレーはコイル側のスイッチがONなので、電流が流れて
電磁石がはたらき、接点は電磁石の力でA接点側に接続されます。
スポンサーリンク
○実際によく使われる型式のリレーを解説致します。
オムロン製 型式 MY2 の場合
コイル側 電圧 DC24V 定格電流 36.3mA
接点側 定格通電電流 5A
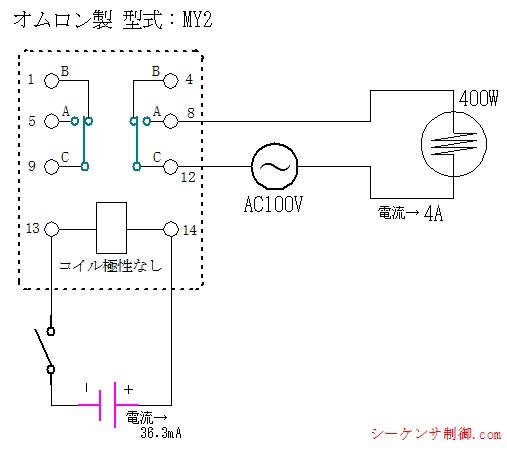
コイル側は約36mAと小さい電流で接点側4Aの大きな電流を制御できます。
○シーケンサ(PLC)からの制御
三菱Qシーリーズのトランジスタ出力ユニットからの出力する場合
下図の様な配線となります。
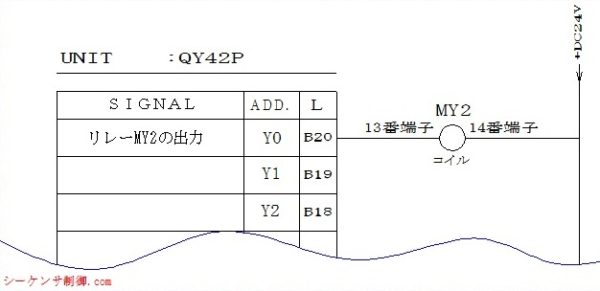
上図の出力ユニットQY42Pはトランジスタ出力の為
流せる(引き込める)電流は100mAです。
オムロン製MY2のコイル側定格電流は約36mAですので
規格内ということになります。
QY42Pに100mAを超える電流で使用した場合は、内部の
トランジスタが破損する場合があります。
これでリレー(継電器)の構造や使い方についての解説を
終了させて頂きます。
最後までご覧頂きましてありがとうございました。
スポンサーリンク
トップページに戻る
当記事は、2016年10月29日時点の情報です。ご自身の責任の元、安全性、有用性を考慮頂き、ご利用頂きます様お願い致します。
当サイトに掲載中の画像は当サイトで撮影又は作成したものです。商用目的での無断利用はご遠慮願います。